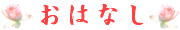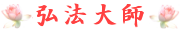阿波北嶺薬師霊場第十一番極楽寺
阿波北嶺薬師霊場第十一番極楽寺
阿波北嶺薬師二十四カ所霊場 開創縁起趣意書
維れ時、平成元年四月二十四日の吉祥日を卜とし、茲に阿波北嶺薬師霊場を開創いたしました。
この慶喜を迎えるに当って開創の縁起並びにその趣意を披瀝し諸賢各位の資といたします。
本霊場は、阿讃山地の明るい南麓に沿って西端は、土成町より東へ80キロ、その道程は長蛇の如く曲折し、
山に野に川をと渡る大変趣向に富んだ観光と参詣に格好のコースです。
この度、阿波北嶺薬師霊場を開いた理由として、この地方に限ってお薬師さまが沢山おられるということ。 それは過去の先人たちが薬師信仰に憧憬を持っておられたことがうなづけます。 現代の人々は、ただ医学だけで治そうとして佛さまの加護のことは、忘れられていますが、 私たちは因縁とか運命などにかかわって生きているという事を自覚すべきです。 病気や災難は、昔より現在の方がはるかに多く複雑化してきました。 病気も昔より現代の方がはるかに多いようですが、然し難病は、昔も今もちっとも変わっていない(癌病) のに気づきます。
お医者さんに薬師信仰についてのご意見を聞きましたら「医者と患者の両方の呼吸が合ったら早く直ると思います…」と。 参拝者とお薬師さんが心如一体となってこそご利益が授かるものだと思います。 又、成仏道の中に三力(さんりき)という教えがあります。 「以我功徳力。如来加持力。及以法界力。」というのがそれであります。 法界の力。多勢の方々の力があってこそ病気を治すことができるのです。 以上のことから今、忘れられている薬師信仰の高揚をはかり、難病災害を除き守護していただき、 大衆の身心共に安楽を願って本霊場を創設いたしました。
今後とも、阿波北嶺薬師霊場に慈愛の眼をお掛けくださいますようお願い申し上げ開創縁起の趣意書と致します。 合 掌

お薬師様は古来より病気に霊験があり、現代のせわしない社会においてはさらに精神的病気もふえてきておりますが、お薬師様の功徳は身体の病、 精神の病、社会の病、この世に存在するありとあらゆる病に効くといわれています。
阿波北嶺薬師霊場第二十一番極楽寺のお薬師さまは当山境内 本堂に通ずる石階段に向かって左側にこじんまりと、温容な姿を見せるのが薬師堂である。
三間四方の宝形造りで本瓦葺き、繁垂木、柱は面取りの角柱で舟肘木で桁を受けている。
本堂より時代は降り、おそらく江戸時代も末期の建立と思われる。
薬師堂の本尊はいうまでもなく薬師如来であるが、立像で、左手垂下するが、五指を軽く曲げ、薬壷をとり、右手屈臂して五指を伸ばすが第三・四指はその先端を軽く曲げている。
像高93.5センチ寄木造で内刳が見られる。室町時代ごろの作と思われる。
阿波北嶺薬師霊場会志納料
- 納経帳(重ねも)
- 二百円
- タオル朱印料
- 壱百円
- 新納経帳
- 壱千円
- 宝印タオル
- 二百円
当山の納経受付時間は午前7時から午後5時までです。当山は予約の電話は要りません。
他の薬師霊場寺院の場合は、お電話で日時ご確認の上、ご参詣下さい。
金泉寺内 (電話088-672-1087)
| 阿波北嶺薬師霊場一覧 | ||
|---|---|---|
| 第1番 | 第2番 | 第3番 |
| 神 宮 寺 | 安 楽 寺 | 和 泉 寺 |
| 第4番 | 第5番 | 第6番 |
| 宝 蔵 寺 | 万 福 寺 | 金 剛 院 |
| 第7番 | 第8番 | 第9番 |
| 宝 嚴 寺 | 東 光 寺 | 金 泉 寺 |
| 第10番 | 第11番 | 第12番 |
| 妙 薬 寺 | 極 楽 寺 | 吉 祥 寺 |
| 第13番 | 第14番 | 第15番 |
| 成 興 寺 | 安 楽 院 | 勧 薬 寺 |
| 第16番 | 第17番 | 第18番 |
| 東 林 院 | 真 福 寺 | 勝 福 寺 |
| 第19番 | 第20番 | 第21番 |
| 長 谷 寺 | 真 楽 寺 | 宝 珠 寺 |
| 第22番 | 第23番 | 第24番 |
| 吉 祥 寺 | 普 光 寺 | 鬼 骨 寺 |