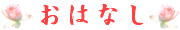極楽寺縁起
極楽寺縁起
四国第二番霊場。当寺は行基菩薩の開基と伝えられる。
後に弘法大師が巡錫(じゅんしゃく)の際、当寺に二十一日間にわたり、阿弥陀経を読誦(どくじゅ)し修法された。
その結願の日に阿弥陀如来がいずこからともなく現われ、大師におことばを賜ったという。
大師はそのお姿を忘れないうちにと、ただちに刃をとって、阿弥陀如来を刻みはじめ、旬日で完成させ当寺のご本尊としてお納めしたという。
ところが、後に、御本尊の後光が鳴門の長原沖まで達し、漁業に支障を与えた。
漁民たちは悩んだ末にこの光をさえぎろうと本堂の前に小山を築いたところ、それからは大漁が続いたという。
「日照山」の山号もそれにちなんでつけられたと云われている。




 世界に比類のない「修練」と「霊験の道場」
世界に比類のない「修練」と「霊験の道場」
讃岐の国に生まれ、後に真言宗の祖となった空海(弘法大師)は、青年時代に一介の求道者として四国の山野を跋歩し、
それら一つ一つの点を霊地と定め、弘仁六年(815年)四国霊場を設定した。
弘法大師の手により、正当に位置付けられた「真言密教」における実践の道場として、高野山と四国霊場がある。
高野山はいうまでもなく、真言密教の根本道場であり、また「女人禁制」の山として、
その性格が象徴されるように密教宣布に不可欠な真言行者の修練の道場である。
宗教における廻教の歴史は古い。イスラム教徒はひたすら「メッカ」をめざして歩み、ヒンズー教徒はベナレスで沐浴する事を終生の喜びと感じ、
キリスト教徒又ユダヤ教徒は涙を流してエルサレムに祈る。さらに仏教徒においてもパミール高原を横断し、
雪のヒマラヤを越え、仏陀成道の地(ブッダガヤ)へ廻国する。
しかし、それら多くの霊地がある国は、一つの点を目指して歩むのに比し、
四国霊場は八十八を点とし、さらに線で結び「発心」の道場から「涅槃」の道場へと大師と
(同行二人)共に歩む。四国霊場の舞台は世界に比類のない、修練と霊験の道場であるといえよう。




top
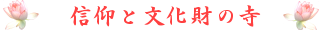 信仰と文化財の寺
信仰と文化財の寺
極楽寺は四国八十八ヶ所第二番のお寺であり、真言宗高野山派に属す。
三方を山に囲まれた閑静な雰囲気の中にあり、宗教的な霊気につつまれている。
もともとこの地方は古くより開かれた土地で、寺の裏山からは旧石器時代の造物が多数出土している。
この地を弘法大師が第二番と定めたのは、さきにも述べたとおり弘仁六年(815年)即ち、千二百年も前のことである。
御本尊阿弥陀如来、その慈愛に満ちたほほえみとやさしさは、拝む人々の心を打ち、
第一級の仏像として国指定重要文化財に指定されている。さらに寺有の「両界曼荼羅」の仏画もすばらしい。
「両界マンダラ」とは、宇宙における多くの「仏」「菩薩」を配置した絵図で、宇宙における真理を表したものである。
寺有の両界マンダラは、徳島県に現存するものの中では最も優美秀作であり南北朝時代即ち、約六百五十年以前のものであり、県指定重要文化財に指定されている。
その他、数多くの宝物を有し、大師堂、薬師堂、観音堂などが現存し、境内の荘厳さをましている。
人々は、もろもろの願いをこの寺に祈る。即ち「子授け地蔵」に子授けを祈り、「安産大師」に安産を願い、弘法大師お手植えの
長命杉(ちょうめいすぎ)に当病平癒・長寿を祈り、来世の幸せを阿弥陀如来に祈る。そこには人々の人生における縮図がある。

top