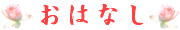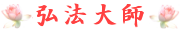厄除祈願
厄除祈願

先人たちは長い経験と知恵の中から災厄に遭いやすい年を見出し、それを「厄年」と呼びました。 この年齢は人生の中での大きな変化の時期でもあり、現代においても家事・育児・結婚・仕事上の責任などといった事で 身体的・精神的にも、疲れが溜まりやすい時期でもあり古くから運気も下がりやすいといわれております。 ご仏前において厄除けのご祈願を受け、仏様のご加護により無事に過ごせますように祈りつつ、 大難は小難に吉祥はより吉祥へとお祈り 致します。 また人生においての節目に仏様と向き合うことで、謙虚な気持ちで生活に望む心構えを持ついい機会へとつながります。
- 受付場所
- 団体納経所
- 必要事項
- 厄除祈願される方のお名前(ふりがな)
ご住所(ふりがな)・数え年 - ご祈祷料
- 5,000円
- 授与品
- 祈祷お札・お守り
- 受付時間
- 午前9時〜午後3時30分
電話受付時間 となっております。
厄年早見表(男・女)
-
令和8年(2026)の厄年(年齢は満ではなく数え年です)
- 男性の厄年25歳 前厄24歳 平成15年生まれ
- 女性の厄年19歳 前厄18歳 平成21年生まれ
- 男性の大厄42歳 前厄41歳 昭和61年生まれ
- 女性の大厄33歳 前厄32歳 平成 7年生まれ
- 男性&女性の厄年61歳 前厄60歳 昭和42年生まれ
- 女性の小厄37歳 前厄36歳 平成 3年生まれ
本厄25歳 平成14年生まれ
後厄26歳 平成13年生まれ
本厄19歳 平成20年生まれ
後厄20歳 平成19年生まれ
本厄42歳 昭和60年生まれ
後厄43歳 昭和59年生まれ
本厄33歳 平成 6年生まれ
後厄34歳 平成 5年生まれ
本厄61歳 昭和41年生まれ
後厄62歳 昭和40年生まれ
本厄37歳 平成 2年生まれ
後厄38歳 昭和64年・平成元年生

「厄除け」の「厄(やく)」の字を辞書で引いてみますと、その意味の中に「くるしみ・わざわい・災難」と載っております。
わかりやすく書き下せば「わざわい(又はくるしみ)よけを(仏前において)祈り願う」となり、さらに進んで積極的・肯定的表現をすれば
「しあわせであるよう願う」お参りとも訳せるでしょう。
当山ではご参拝の方御祈願の方がしあわせであるよう、祈願を続けております。
夫婦や親しい友人同士また家族がお互いが元気で幸せを願いあうという、あたりまえのことがことが何よりも大切であると信じています。
善い願いを自分に向けてくれるような自分を再認識する場として、またご自身に反映させていくよう、ご仏前において誓い願われますことを
私共は「祈願」とよんでおります。
厄年に当たる年齢の方、日常で様々なことがありお参りしようと思い立った日を吉日として、ご一緒にご仏前において「厄除」を如法に祈念しております。
又ご祈願終了後、ご祈祷いたしました「御札(おふだ)」ならびに御守(おまもり)を授与(じゅよ)致しております。
 当山へお参り出来ない方へ
当山へお参り出来ない方へ
本来ならばご本人様がご来山され、ご祈願されることが望ましいですが、
体調・仕事・遠方の為といった理由でお参りできない場合は、
代理の方がご祈願を受け、お札を受けられても構いません。
また諸事情によりお参りできない方の為に、郵送でのお申し込みも受付しております。
便箋に下記の必要事項を記入の上・ご祈願料を添えて、現金書留にてお申し込み下さい。
- ご希望の祈願名
- 厄除祈願
- ご祈願料
- 5,000円別途送料700円がかかります。
- 必要事項
- 厄除けを願う方のお名前(ふりがな)・ご住所(ふりがな)
お電話番号・年齢(数え年) - 授与品
- 祈祷お札・お守りはご祈願後
発送いたします。 - 送り先
- お札・お守り等を発送する宛先をご記入下さい。
 郵送での宛先
郵送での宛先
- 郵便番号
- 779-0225
- 住 所
- 鳴門市大麻町桧
- 宛名
- 厄除祈願
極 楽 寺 行
電話受付時間 となっております。